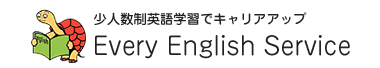横溝正史や江戸川乱歩にどっぷりとつかった時代に、読書を楽しんだ人間なので、このところ、話しの筋が、あまりにもオーソドックスなタイプの[探偵小説]から逸脱してしまい。世評的にはともかく、私個人としては残念だな、と思うことが多かったのですが。久しぶりに、こうした雰囲気を楽しむ事の出来る作品が、このところいくつか出てきて、渇をいやしてくれます。
萩原真理さんという方は、まったく存じ上げなかったのですが、「呪殺の島」というタイトルにひかれて買いました。
海上の孤島。
昔からの呪いの伝統を持つ、一族が住む島。
赤江という一族は、はるか昔から、呪いの人たちとして有名で、その一族も、一人、また一人と、命を失っていく。
曰くのある島に呼び出された、秋津真白と古陶里(ことり)の二人。
真白は、この一族のひとり。
古陶里は、その親友、付添として。
この島を実質支配しているのは、小説家として著名な赤江神楽。
秋津真白が目を覚ました時、自分の手には血塗られたナイフがあり、近くには、血まみれの赤江神楽の遺体があった。
いったい何が起こったのか?
自分は何をしでかしたのか?
その時、真白は気づく。
自分は、何も思い出せない。
そもそも自分は何者なのか。
「秋津真白」という名前さえ、周りの人たちに言われて初めてそれが自分の名前なんだということを教えてもらうありさま。
だから、ここに集まっているメンバーの関係も、名前も、まったくわからない。
横溝正史の「八つ墓村」のように、歴史も、地域の特質も、人間関係も、何もわからないままに、知らない村に入れられて、周りの人たちの、行為とも悪意ともしれない。扱いに困惑しながらも、すこしずつ状況を飲み込んでいく、という雰囲気。
夢野久作の「ドグラ・マグラ」のように、頭には残っていない「記憶」を求めてさ迷い歩く、主人公。いろんな人が、さまざまなことを声高に語り、「知っていること」を前提に話されるけれど、その前提が、まるで理解できない中で。自分は誰の言うことを聞いて、何をしたらいいのか、当惑してしまう。
当たり前のことだけれど、手に持っているナイフ、足元に倒れ伏す、叔母であるはずの赤江神楽。
「おまえがやったのか」「忘れたふりをしているのもいい加減にしろ!」自分に向けてむけられる罵声。
それでも、自分の記憶には、この叔母とされる人との関係は全く見えてこない。
「私は仲間だぞ。いつでもお前のことを信じているし、守ってやるからな」
私の「幼馴染」であり、「親友」だという、和風の端正な少女「古陶里」。
久々のページをめくる手ももどかしく、次々と起こる恐怖の展開に、目を回しそうになりながら、終わりまであっという間に読み終えました。
感想は、「とてもおもしろかった」につきます。
手が空いている間、いつでもページを開いて読みたくなる本でした。
ありがたいことに、すでに「続編」も出ています。
「巫女の島 呪殺島秘録」が同じ新潮社から出されています。
これまた楽しみです。