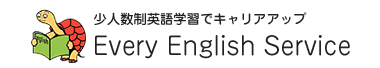訳というものは、時として裏切り者になってしまうことがあります。
岩波文庫から【紫禁城の黄昏】という本が出ています。
これは映画「ラスト・エンペラー」の原作としても知られた有名な本ですが、実は原典の約半分程度にあたる前半と中途の一部を訳しておらず、その理由として、「主観的な記述だから」と訳者は述べています。
これによって、日本に対する記述が、作者の考えとはかなり違った印象を与えるものになっていることは事実です。
数年前、渡辺昇一さんが全訳をされて、ようやくその全貌が明らかになりました。
実際に目を通してみると、初読(岩波文庫)の時と比べると、かなり分量も多く、そのトーンの違いに驚かされました。
インターネットで、カナダの書店にあった原著を取り寄せてみましたが、やはり改訳版は、原文に対して(つまり作者に対して)忠実であるように思います。
竹内均・訳、【自助論】という本があります。
サミュエル・スマイルズという英国の作家が書いた本ですが、明治時代にベストセラーとなって、現在でも手軽に文庫本で読むことができます。
三笠書房の【知的生き方文庫】におさめられているこの本は、抄訳です。
原文訳は【講談社学術文庫】に収められていて、タイトルも明治に出されたままの「西国立志論」という題名のまま、中村正直・訳で出版されています。
この2冊を読み比べてみると、かなり印象が違います。
竹内訳は、もちろん最近の訳本ですから、文章も読みやすいし、何より量が少ない。活字も大きいですから、とりつきやすい。
ただ、原版と比べると、「自助論」をベースにした竹内均版の「人生講談」の趣があります。
「西国立志論」は、活字もぎっしりで、厚さも2倍ほど、内容量からすると、数倍のボリュームと言ってもよいでしょう。
竹内版「自助論」が、いわば勝ち組、負け組を正当化する、自己責任論に終始しているのに対して、「西国立志論」はどちらかというと人間の生き方に対する指導書的な書き方をしています。
わたしたちは、ついとりつきやすいということで、抄訳に頼ってしまうことが多いのですが、抄訳は、ある意味で、訳者の創作に近いものがあることも、心に留めておかなくてはならないようです。
この項は、宮崎学さんの『「自己啓発病」社会』(祥伝社)を参考にさせていただき、田口が確認をさせていただきました。