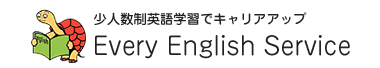戦後の推理小説のファンの方なら、名探偵・神津恭介の名前に聞き覚えのない方は、ほとんどいらっしゃらないと思います。
当時の大物作家である江戸川乱歩氏の推奨を受け、ほとんど小説一本を丸ごと、雑誌として出版された、「刺青殺人事件」。
これには、日本家屋での密室殺人事件という、当時としては画期的な、トリックが含まれていました。
もちろん、それ以外にも、バックグラウンドを彩る、入れ墨の美学も相まって、独特の雰囲気を持っている作品でした。
この作品で、多くの好意的な評価を受けた高木彬光氏は、ひきつづき、「能面殺人事件」を書きます。
これは、いうなれば、折原一さんが書いているような、叙述トリックとてもいうべき作品で、発表の翌年、探偵作家クラブ賞(当時の日本推理小説協会賞)を受賞しています。
ただ、私としては、残念なのは、この探偵作家クラブ賞は、「刺青殺人事件」の業績と合わせての受賞になっているところです。
たしかに、この作品には、推理小説ファンの「未読の本格推理小説の犯人を明かさない」というタブーを破っているところもあり、いささかファンの怒りを買うところもあります。
また、「刺青」と違って、話しの進行がまっしぐらで、全体の持つ余裕というか、余韻というか、そういった趣が弱い、ともいえるかもしれません。
でも、この作品は、私が初めて手にした、文字通り、[大人向け]の本格推理小説であったこともあり、読了後、夢中になって、もう一度冒頭から読み直し、書かれているトリックを確認して、あらためて、高木氏の綿密な作品構築に感服した、という経験があります。。
その後も、折に触れ、この作品を読む機会に恵まれました。
この作品は、昭和21年の夏に、作者、高木彬光が、旧友、柳光一と再会するところから始まります。
彼は、恩師、千鶴井博士の下に寄宿し、専門の化学の研究を行っているのですが、千鶴井博士はなくなられ、奥様は精神病院に入院されている状態。以前、彼が思いを寄せていた娘さんも、精神的な安定を失ってしまっている、という悲惨な現状です。
その中で、互いに分かり合えないどころが憎しみ合っているとしか思えない家族が、一つ屋根の下で暮らしているのです。
まさに一触即発の空気の漂う、名家で、次々と事件が起こり、人が死んでいく・・。
柳光一の手記の形でつづられていく、日々の記録は、淡々と描かれていきます。
まさに、高木彬光が、[理想の形の推理小説]と形容した、「探偵が、推理をしながら、それを記録として残していく形」というスタイルそのままに、恐るべき殺人者の計画が進んでいきます。
私は、小学校6年の時、通っていた塾の先生に、[本が好き]と漏らしたところ、春陽文庫の「能面殺人事件」と、河出の全集版のドストエフスキーの[罪と罰]を貸していただきました。
ドストエフスキーは、本自体も、作品そのものも大変な大作で、読み終えるまでに1年近い日々を費やしてしまいましたが、「能面殺人事件」は、先帆とも書いたとおり、寝る間も惜しんで読みふけり、一晩で読み切ってしまいました。
申し訳ないと思っているのは、その後、先生は転居されてしまい、2冊とも、返却する機会を逸してしまったこと。
どちらも、その後の私の人生に、大きなショックと、印象を残してくれた本でした。
もしかしたら、本好きになるきっかけを作ってくれた2冊かもしれません。
「能面」の真相は、まさに衝撃そのもので、本当に何度も読み直し、自分の頭では、矛盾を見出すこともできず、感服したものです。
最近、たまった本をかたずけていて、「能面殺人事件」を見つけました。
その場で、立って読み始め、そのまま、終わりまで読んでしまいました。
いまでは、光文社や、角川をはじめ、各社から出版されているようです。
ヴァン・ダインの「グリーン殺人事件」などの作品の犯人名が出てきます。
このあたり、未読の方は注意される必要があります。
そうした警告を発しなくてはならないとしても、これは、読むべき日本の名作だとおもいます。
ぜひ、書店で目にされたら、とりあげて、始めの数ページに目を通してみてください。
もう一つの大傑作にお目に書かれるかもしれません。